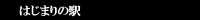
―――目を開けるとそこは見知らぬ駅のホームだった。
駅は古びた木造立てで、どこか懐かしささえ感じさせる構えだ。
ただ腐食が激しく、それにより陥没したと思われる箇所が何処かしこに在る。
木張りの床は一歩踏み出すたびにギシギシと鈍い音を立て、
苔が張り付き滑りやすくなっている処もあった。
わたしは足元に細心の注意を払いながら辺りを探索することにした。
駅周辺は一面の絨毯と見紛うほどの鮮やかな金色の稲穂畑が
遙か地平線の彼方まで続いていた。
線路も共にその先へと消えていて、次の駅(あるいは前の駅)の
存在を確認することはできない。
畑の所々には衣服がボロボロに剥がれ落ち、もはや原型を留めていない案山子や、
大きな目玉を模った人形が置かれてはいるが、それ以外には何もない。
駅のなかには改札がひとつと、こぢんまりとした車掌室があるだけ。
ホームには駅名も何も書かれていない看板と、ペンキの剥がれ落ちたベンチ。
そして点くとも知らない背の低い水銀灯があるだけだ。
―――と突然、わたしはなんとも言えぬ心細さに苛まれた。
「他に誰も居ないのか?」
「この駅で待っていても何もやってこないのでは?」
「そもそもここは何処なんだ?」
様々な悲観的な考えが頭の中で交錯した。
わたしは気持ちを少しでも落ち着けようと、近くにあったベンチに腰を下ろした。
するとまもなくである。
そんな不安を掻き消すかのように、地平線の向こう側から
モクモクと生き物のようにうねる黒煙を吐いた蒸気機関車が姿を現した。
previous<< >>next